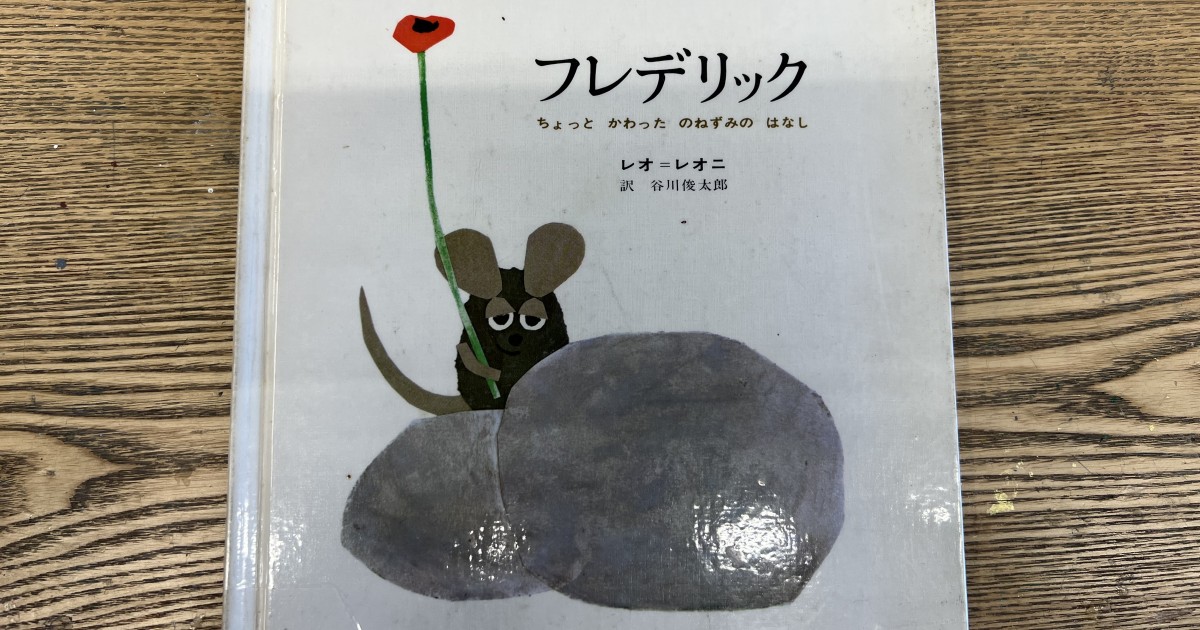“情景”を描くことからはじめる
仕事がはじまった。「わくわく!」みたいな言葉で無理に鼓舞することなく、年末年始で別な「日常」が染みついていた身体を、また仕事が真ん中にある「日常」に戻していく。その新しい一歩目をただ踏み出していく。
ぼくたちの学校は、5年前、理事長と校長の“情景”を通したやり取りからつくられていったという。(開校以前はホームページに掲載されていたそう)
そこから5年。描かれた“情景”のようなものが目の前で起こっていることもあれば、もう過去になってしまった“情景”もあって、間違いなくぼくたちには新しい“情景”が必要になっているんだと思う。
ということで、年初めの最初の仕事は、“情景”を描くということからはじまったわけです。
とはいえ、
そもそも何で“情景”なんだ?
“情景”を描くことの意味は何?
描かれた“情景”を仲間たちとどう分かち合っていけばいい?
僕は“情景”のことはよくわからないので、僕なりに年末に動きがはじまってからずーっと考えてきた。
そんな中、元旦に読んでいた『変調「日本の古典」講義 身体で読む伝統・教養・知性』(内田樹、安田登著)にはこんなことが書かれていた。(この本年明け一冊目だけど超おすすめ)
前にもお話したことがありますけれど、「軒下から『雨降ってきたかな?』とそっと手を差し出す」動作なんていうのは、みごとに身体が整うんですよ。手のひらがわずかな雨滴でも感知できるように感度を上げるためには、腕の筋肉の緊張があってはならない。どこにと力みもこわばりもないように、柔らかく手が伸びていないと、手のひらにぽつんと落ちる最初の雨滴なんて感じ取られませんから。人間て、なかなかすごいもので、そういう情景を思い浮かべてもらうと、それだけできれいにそういう動作ができる。(p179 第3章 身体感覚で考える)
“情景”を思い浮かべると、それだけできれいにそういう動作ができる。思い浮かべられるということが身体を動かしていく感じかな。
長く指導して分かってきたことの一つは、「存在しないもの」、今の場合でしたら「空から降ってくるかもしれない最初の一滴」というものを想像してもらう。そうすると、身体がきれいに整のう。「手のひらに落ちた雨滴」じゃないんです。「落ちてくるかもしれない雨滴への期待」なんです。それには身体を整える働きがある。これを「あなたの右腕を手のひらを上に、右斜め上方迎角60度で20センチに差し出してください」というような指示を出すと、もうがちがちになってしまう。つまり現にそこにある現実の身体を意思によって統御しようとすると、身体はうまく動かない。でも、「そこにないもの」を想像的にどうにかしてみてと言うと、きれいに動く。僕はこれに気づいたときに、人類が「物語」というものを必要とする理由はこれじゃないかな…とふっと思ったんよね。(p179 第3章 身体感覚で考える)
落ちてくるかもしれない雨滴への期待。そうか、「期待」か。そして、まだ「そこにないもの」を想像することで身体がきれいに整う。“情景”という「期待」が込められた「そこにないもの」。そうでないと「そこにあるもの」ばかりに目がいって、どうも「指示」が増えてがちがちになってしまう。
いわゆる「子ども像」とか「教育目標」とか「ビジョン」とか、そういった質感のものとはまた違った別なものであることは何となく感じていたけど、“情景”を描くことの意味が少し見えてきた気がする。
期待が込められた、思い浮かべることができる、まだそこにない物語。
これを僕たちの間で分かち合いながら学校づくりを進めていくということの意味は、やってみないことにはまだまだわからない。
それでも、僕たちの学校は“情景を描く”ということからはじまっていったことは紛れもない事実としてそこにあり続けることを思うと、やってみることの価値は大いにありそうだ。
よくわからないまま、とりあえず中心となってやってきたのは、そんな予感があったからかな。
今ある枠組みから考えはじめると、それこそどうしても「指示」的なものになって、みんな身体ががちがちの不自然な感じになってしまう。(もちろん、今ある枠組みから考えていくことも大事)
動き出しくらいは、「こうなったらいいなあ」を思いっきり描いてみる、それを物語として仲間と分かち合えるような形にして、そこから共につくっていく。そうであったらいいなあと思うな。
引き続き、手足を動かしながら考えていきたいと思います。
最後に、仕事がはじまる前に僕がザーッと一筆書きで書いてみた“情景”の下書きをここに残しておきます。(恥ずかしいので、以下、購読者限定で←なんで笑)